|
|
2007年2月前半
『僕は妹に恋をする』(監督安藤尋 出演松本潤、榮倉奈々)をMOVIXさいたまで観る。
最近、コミックスの実写映画化が多い気がするが、これもそういう一本。
映画の雰囲気は好きである。最近洋画よりも日本映画の方が興行的に成功していているが、映画自体はどちらかというとテレビドラマ的でエンターテイメントに徹している。主演に松本潤と榮倉奈々を迎え、いかにもそういう一般受けを狙った映画かと思わせるが、むしろ正反対の静かで美しい映画。始まって比較的早い頃に双子の兄妹の頼が郁に好きと告白しキスをするラブシーンなど、観客の息も聞こえるくらい静かで緊張を高める。それ以外でも、全般的に音楽はギターを中心にした静かなメロディが流れる程度。担当は大友良英だ。
そんなわけで、松本潤狙いかエンタメを期待してきたと思しき観客は退屈そうでうるさかった。シネコンで観たのが失敗。ミニシアターに行くべきだったかもしれない。
監督は安藤尋、魚喃キリコのコミックスを映画化した『blue』の監督である。『blue』は原作が好きで観たかった映画だが見逃した。観ていないのでこの映画の出来は判らないが、映画を観ていて原作の『blue』をふと思い出すところが何度かあった。
頼と郁の恋が物語の中心だが、二人を好きになるもう二つの恋も描かれる。中でも、頼の親友の矢野の恋が秀逸。『blue』を思い出したのも矢野のエピソードのためかもしれない。
ただ残念なのは雰囲気は好きだけど、感動というほどのものはなかった。双子の兄妹が互いを好きになってはいけない、なのに抑えられないほど好き、というのが今ひとつ伝わらない。繰り返しになるけれど、本筋ではない矢野の恋の方がいい感じ。ただ、説明過多という気がするが。静かに物思いにふける時間が流れるだけで伝わるものがある。そこで留めておけばよいのに。
permalink | 
金曜日に出かけるのが面倒くさいなぁというのが始まりだった。金曜の夜はだらだらと過ごす。寝る前、異様に眠いと思いながら寝たのだが、翌土曜日は18時まで寝ていた。出かける予定があったのにその気力もでないまま。
土曜の夜もだらだらと過ごして、少し早めに寝る。どうも風邪を引いたらしいと思う。鼻が少しつまり気味、なんとなく頭が重くて、肩凝りがひどい。そして今日もまた延々と眠り続けて、14時半まで寝続ける。
昼間、2巻まで読んで中断していた『マルドゥック・ヴェロシティ 3』(冲方丁 早川文庫)を数日前からちんたら読んでいたのだが、今日残りを一気に読み終える。
読むのに時間がかかったのは、単語の羅列のようなちょっと変わった文体のためもある。前作もこんなに読みにくかったかなと思って、本棚から『マルドゥック・スクランブル―The First Compression 圧縮 』(冲方丁 早川文庫)のシリーズを確認すると、こちらは普通の文章だった。
この書き方は、場面を映像的に喚起させるところがあるのだが、こればっかり続くとかなり読みにくい。話は、ウフコックとボイルドの決別までの話で、『マルドゥック・スクランブル』をもう一度読み返さなくてはと思った。
夜、まだまだ調子悪いので21時頃から3時間ほど寝る。0時に起きると少し気分がいい。この週末は何も進んでいないが、休養ということで。まだ頭が少し重いが、このまま回復すればいいのだけど。
permalink | 
『マリー・アントワネット』をMOVIXさいたまで観る。
ソフィア・コッポラの新作。マリー・アントワネットは、実はただノーテンキな女の子だっただけという映画なのかと思っていたが、想像とちょっと違った。音楽ももっとロック一杯の音楽映画みたいなノリなのかとも思っていたし。でも実際にはちょっと悲しい話。
マリー・アントワネットは結婚のためにオーストリアから一人でフランスに文字通り身一つでやってくる。国境でお供はもちろん、愛犬も引き離され、慣習としてすべて身に着けているものも脱ぎフランスのものに着替えさせられる。
そしてフランスに着いて後のルイ16世と結婚するが、ルイ16世はマリーに触れようともしない。子供のできないマリーは、次第に宮廷での疎外感を深めていく。そんな中でマリーはドレスや夜会、ギャンブルなどの浪費を始める。
マリーはノーテンキな女でも派手好きでもわがままでもなくて、ごく普通の女の子として描かれる。ただおかれた立場が特別だった。ごく普通に自分のささやかな幸せを求めていたら、いつのまにか負債の王妃となっていた。最後には民衆たちがヴェルサイユに押し寄せてきた。これも唐突で不思議な出来事のようだ。
案外マリー・アントワネットにとっては本当にそういう人生だったのかもしれない。最後も悲壮感はなく終わる。
残念なのは時間の流れがちょっと速すぎるように感じたこと。マリー・アントワネットの半生を描くには、2時間は短すぎたんではないか。あと、キルティン・ダンストは可愛いんだけど可愛いだけじゃだめでした。映画としてなんとなくつかみ所のないまま終わってしまった。
permalink | 
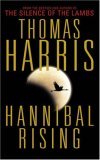 昨日、『マリー・アントワネット』の前の予告で、知ったのが映画『ハンニバル・ライジング』の公開。ハンニバル・レクター博士の若き日の話らしい。トマス・ハリスのそんな原作は知らないぞ。と思ったのだが、もしかして知らないうちに出ていたのかと思って調べたら、翻訳はまだだが原作はあった『Hannibal Rising』(Thomas Harris)。
昨日、『マリー・アントワネット』の前の予告で、知ったのが映画『ハンニバル・ライジング』の公開。ハンニバル・レクター博士の若き日の話らしい。トマス・ハリスのそんな原作は知らないぞ。と思ったのだが、もしかして知らないうちに出ていたのかと思って調べたら、翻訳はまだだが原作はあった『Hannibal Rising』(Thomas Harris)。
予告で日本の鎧が出てきたので妙に思ったのだけど、Webを検索してちらほら見かけた中に、ハンニバルの育ての親が叔父の妻で日本人とか書かれていた。情報が正しいか未確認だけど、なんとなく原作本を含めてトンデモ本、トンデモ映画になってないかと気になってしまうのは僕だけなのか。
映画はアメリカで2月公開、日本でもゴールデンウィークには公開らしい。
permalink | 
『どろろ』をMOVIXさいたまで観た。
『どろろ』については期待と不安が半々だった。結論からいうと、部分的には期待以上、駄目なところもあるけど全般的には気に入った。そしてその駄目なところも「だって漫画だし」と許せてしまう。
期待と不安が半々だったのは、は監督が塩田明彦だったからである。塩田監督の作品は、『害虫』や『カナリア』はすごく好きだけど『月光の囁き』や『黄泉がえり』はちょっとというところがあって、全く予想がつけにくい。『害虫』みたいな映画を撮る一方で、『黄泉がえり』で興行的にも成功したりしているわけで、『どろろ』を商業的に撮ると『黄泉がえり』みたいになってしまうのかなと思った。ただ『どろろ』というのは魔物に躰の48箇所を獲られた百鬼丸がほとんど主役のような話で、今の時代にドラマ化しにくいと思うのだが、そういうグロテスクなものを扱わせたら塩田監督の得意技なんではないかという気もする。
一見、商業主義、その実グロテスクな面で好き勝手やり放題という映画になるなら、期待してもいいんじゃないか。『月光の囁き』なんていう映画を撮った監督のことだ。しかし、そうはいっても…、とまあいろいろ想像を膨らませて、勝手に期待したりしすぎないようにしていたのだ。
映画が始まって、泥臭い歌声の音楽が流れ始めた時点でちょっと期待してもいいんじゃないかという気になった。百鬼丸が最初の魔物と戦うシーンは、踊り子に化けていた魔物が招待を現すと蟹のような蜘蛛のような姿で、ものすごいスピードで壁や天井を這い回ったりして、すごく嬉しくなった。この辺は期待以上。
ただ、その後の魔物たちのクリーチャーがいまいちだったけど。アクションは、ワイヤーアクションを多用していて、もうちょっとアクションのメリハリというか、戦いにストーリー性があればよかったのだが、まあそれはよしとしよう。
百鬼丸の躰が、義手義足の作り物で出来ているわけだが、漫画やアニメならそれで済んでも映画になってしまうとただの義手、義足ではリアリティがない。それを呪い医師の作った呪術的なものにすることで物語的な納得をさせてくれる。48個のパーツを作るところでは、エレキテルを流すとかSFXというより特撮という感じの雰囲気で、わざとやっているんだろうけれど漫画チックでそれもまたいい。包帯だらけの子供百鬼丸に電流が流れるところなんか、もうフランケンシュタインの誕生みたいだ。
そういう意味じゃ、たくさんの映画のオマージュみたいなものもあったように思う。百鬼丸の生まれるところは『フランケンシュタイン』、最初の魔物の踊り子たちのいる酒場は『スターウォーズ』のジャヴァ・ファットの宮殿を思い出したし、子供を食う魔物の話では『エイリアン』の卵みたいなのが出てくる。なんかそういう、雑多でごった煮的なところも好きだ。
結構話は作り替えてあるようでいて、百鬼丸誕生のエピソード、鯖目とマイマイオンバの話や、ばんもんのエピソード、どろろの両親との別れ、父親との最後の対決など要所要所では原作に拠っていて、原作との違いの不満もあまり感じなかった。ある程度原作に忠実だと違いが気になるし、変えすぎれば原作と違いすぎると不満を感じる。適度に離れ、適度に近い、原作やアニメとの距離感が丁度よかった気がする。
最後、倒さなくてはならない魔物が残り24体と出るのは、続編を作るってことか。続編が作れるほど興行的に成功していないんじゃないかという気がするが、ぜひ作ってほしいなぁ。
permalink | 
『魍魎の匣』があったのでリンクしておく。もう1月くらいからあったみたいだけど、今日気づいた。内容はまだ製作発表レポートしかない。
出演者が盛んに前作とは違うキャラと繰り返していたり、アドリブが多そうだし、笑いのシーンも多いみたい。京極堂シリーズの原作にはそういう要素はあると思うけど、そればかりいわれてしまうとちょっと気になる。
permalink | 
 『ドキュメンタリーは嘘をつく』(森達也 草思社)を読む。
『ドキュメンタリーは嘘をつく』(森達也 草思社)を読む。
きっかけは、同タイトルのテレビ番組を偶然観たからだ。番組はこの本をベースとしてテレビ番組化したもので、何人ものドキュメンタリー作家にインタビューをすることでドキュメンタリーとは何かを明らかにする、という体裁をとりながら「ドキュメンタリーに嘘をつかせる」。
番組のドキュメンタリー作家たちの話も面白かったが、最後の展開がひとひねりあって面白いと思ったのだが、今回この『ドキュメンタリーは嘘をつく』を読んで、そのひねりは別にドキュメンタリーにとって特別なことではなくて普通にあることなのかしもれないと思った。
『ドキュメンタリーは嘘をつく』の主張は一言でいうと、「ドキュメンタリーとは事実と真実の集積ではなくて、あくまで作る側の意図によって再構成されたフィクションである」ということだ。簡単にそんな一言にまとめられないと思うし、森達也本人にいわせたら、俺はそんなことは一言も言っていないといわれしまうかもしれない。ただドキュメンタリーは被写体は役者ではないし、演技するわけでもない、台本もなければ、そのままキャメラに写ったものを編集した、客観的なものだと思っている人が多いことに対してそうではないということを明らかにしている。
1章で森達也のドキュメンタリー作家になるまでの遍歴、2章ではドキュメンタリーの歴史、3章ではオウム以降の森達也とドキュメンタリーのかかわりが書かれる。ここまででドキュメンタリー入門担っていると思う。オウム以降の森達也というのは、森達也がオウムについてのドキュメンタリー『A』、『A2』で有名になり、逆にそのためにテレビ局との折り合いが悪くなり、ドキュメンタリーを撮ることが本業のはずなのに、むしろ自主制作のような形でしかそれができないでいる。その辺の経緯は、4章以降でたっぷり書かれている。
プロローグには、「観る側」と「作る側」の二つの視点からドキュメンタリーという表現ジャンルの解析をすると書かれているが、「観る側」は「作る側」にも存在する。「作る側」というより「撮る側」すなわちドキュメンタリー作家たち、「観る側」というよりテレビ局などの制作側も含む撮られたドキュメンタリーを受け入れる側の意識の違いがあるように思う。
テレビ番組『ドキュメンタリーは嘘をつく』を観る前から、ドキュメンタリーは事実の集積ではなく、作家の意思が強く含まれているとは思っていた。だからこの番組の内容自体にはそれほど違和感を感じなかった。この番組の最後で、面白いなぁと思ったのは「ドキュメンタリーではこういうことはやらないものだ」と思っていたからだ。
しかし『ドキュメンタリーは嘘をつく』を読んで、それは決して珍しくないのだということを知った。ドキュメンタリーに含まれる作家の意図は、編集やナレーションだけでないことも、言われるまで気づかなかった。いや疑問に思ったりすることはあっても、これは事実なのだと深層心理で感じたことを訂正していたりもするのかもしれない。ドキュメンタリーの中に含まれる嘘は、想像していたよりずっと奥深いものだと思った。
permalink | 
『墨攻』を新宿ミラノで観る。
原作は日本のコミックスだが、そのコミックスの原作は酒見賢一の『墨攻』である。コミックスの方は読んだことがなくて、その元の『墨攻』は好きな小説である。となると、どうしても小説『墨攻』との違いが気になってしまう。
映画と原作は別物と思っているが、どうも始まって早々に原作の原作『墨攻』との違いが気になって仕方なかった。というのも、物語のディテールの違いではなく、タイトルの「墨攻」の意味からして違うような物語の始まり方がどうも引っかかった。
「墨攻」とは、確か酒見賢一の造語で「墨守」をもじったものである。「墨守」とはこの物語の主人公革離の属する墨子という集団が攻めることなく守ることに長けていたことを由来にする熟語である。従って、物語もまた城を守ることで生き延びようとする話だ。守るだけでなくて、一人の墨子で二万の敵、映画では十万の敵に対抗できるわけはない。にもかかわらず、映画では守ることより、攻撃的な印象が強い。城に入って早々、早速矢に細工をして飛距離を伸ばして敵に脅しをかけたり、民衆たちに戦うことを説き始める。
他にも原作では、墨子の革離が一人現れた際、墨子が集団で援軍を引き連れてやってくると思っていたにも関わらず、たった一人革離のみが現れたことに驚くが、映画では革離一人が現れたことに驚きもしない。
墨家は報酬を求めないため革離も寝所として下男部屋の隅でも用意してほしいと望み、案内された薄汚い部屋で藁にくるまって寝る。映画でも馬小屋に案内され、そこで寝るよう言われるものの、それは王の息子の指示で革離の希望のようには説明されない。
そういう墨子のあり方などの描き方が全然違うことが、どうもいちいち引っかかってしまったのだ。一人対十万という、戦争スペクタクルなので、原作の原作の酒見賢一の世界とは全く別物なのだとわかっていても、最低限物語の背景としてそのままにしてほしかった気がする。
すぐに話は篭城戦の話になってしまい、そこからは戦争スペクタクルなので、酒見賢一の小説とは全く違う世界になる。全く別物として観るが、ちょっとカタルシスの得られない映画だった。最後はメロドラマになっちゃうしね。
permalink | 
昨夜は3時を過ぎても眠くならないので、無理に寝ないでそのまま起き続ける。外が明るくなってきたところで、コーヒーを飲んだり朝食を摂ったり、録画したドラマを観たりする。
10時過ぎて眠くなってきたので、日向ぼっこしながら居眠り。昼前には目を覚ます。
午後、サイト更新を始める。露地林だけ、デザインを合わせないまま、リンクの更新も放置したまま1年たってしまったので、とりあえずデザインを合わせてサイト本体に組み込む。
一年も経っているので、リンク切れはたくさん出来ているだろうし、最近よく見るサイトとはずれが出来ていると思うが、リンクの手直しは今日はやめておく。徐々に使えるリンクにまた整えていきたい。
permalink | 
『愛の流刑地』をMOVIXさいたまで観る。
渡辺淳一の原作は未読。始まってしばらくすると、どこかで観たような話だなぁと思ったのだが、結局『失楽園』と同じパターンなんじゃないかと思ったのであった。『失楽園』では最後に二人の心中で終わるけれど、『愛の流刑地』では作家の男が不倫相手の女を愛していながら殺すことで始まる。もちろん、時間の流れも殺したところから始まり、裁判と回想を通してどうしてそうなったかというそれまでの経緯が描かれる点は違うが、不倫の果てに死を選ぶ結末という大筋が渡辺淳一的だなぁと思った。まあ、不倫の果てに死を選ぶ結末って、俳句より短い言葉に要約して似てるとかいうのは失礼だとは思うが、二時間の映画で三分の一くらい濡れ場では似てる気がしても仕方ない。そういう意味では、映画になってしまうと渡辺淳一も二時間サスペンスドラマ並みになってしまう。
それともうひとつ、長谷川京子演じる検事が胸元の大きく開いた服を着ていてすごく違和感があった。最初は何か意図があって、わざとそういう服装をしているのかと思ったが、そういう説明はなし。登場人物としては寺島しのぶが演じた殺された女性の気持ちを代弁する役割を一部もっている重要な役のはずなので、台詞にはない検事の意図があったのかもしれないが、映画を観ているだけだとよくわからなかった。
どこかで観たような話と思ったのに、後半予想外にぐっと来た場面が二回ほどあった。作家の豊川悦司が裁判では誰もわかっていないと叫ぶところて、女の母親役の富司純子が事件当日の様子を語る場面だ。まさかそんな風に感じるとは思わなかった。よかったといえば、ほんの少ししか出てこないが、貫地谷しほりの作家の娘もよかった。
濡れ場が多い割には、無駄なシーンとは感じなかったのはそういう物語だからだろう。逆に足りなかったのは、裁判での検事や弁護士の話すシーンは少なくて物足りなかったし、やっぱり殺された女がどういう気持ちを持っていたかが伝わりきらなかった気がする。母親の証言と最後の獄中に届く一冊の本に隠されたメッセージで、理由は明かされるけれどもうちょっと理屈でないものがほしい。
豊悦の作家が独白する「選ばれた殺人者なのだ」という言葉がピッタリこなかったが、女性の気持ちが伝わらないとその通りだと納得もできなけれど、作家の思い込みだとも言い切れない。そこがすごく宙ぶらりんな気持ちになった。
原作を読むつもりは特になかったのだが、そういう感情が描かれているのかどうかが気になってしまった。
permalink | 
『守護神』をMOVIXさいたまで観る。
ハリウッド・エンターテイメントらしいエンターテイメント。沿岸警備隊で、海難救助をするレスキュー隊員のケビン・コスナーがバディを事故で失う。精神的な痛手を受けた彼はレスキュー隊訓練学校の教官として、しばらく現場から離れることを余儀なくされる。その学校にやってきた訓練生たちの中に、水泳は得意だが記録を更新することにこだわる訓練生アシュトン・キャッチャーがいた。
というわけで、冒頭の嵐の中の海難救助のあとは、ほとんど訓練の話なのだが、これが結構いい。訓練だけで映画が終わっても別に構わないかも。最後30分くらい、海難救助に出るアシュトン・キャッチャーと現場に戻ったケビン・コスナーのレスキューがクライマックス。「守護神」というタイトルの意味もここで明らかになる。
なんとなく、ケビン・コスナー版「海猿」という感じもしなくもないが、2時間半くらいあるけど、長く感じさせない普通に楽しめる良質なエンターテイメント。屈折したのが好きな僕やあなたにはちょっと物足りないけどね。
permalink | 
『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』をMOVIXさいたまで観る。
フジテレビをつけるたびにCMとCM番組がガンガン流れていて、ちょっと食傷気味。だけど、ちょっと観たい気がしたのはタイムマシンものであるのと、行き先がバブル絶頂時代というところか。タイトルロゴも『バック・トゥ・ザ・フューチャー』だし、車型タイムマシンの代わりにドラム式洗濯機型タイムマシンと、もう設定からパクリなので、コメディタッチのSFじゃなくて、この設定で単純にバブル時代を笑い飛ばそうというSFチックコメディなのは明らかである。
そういうつもりで観たら、意外と始まりの設定が凝っていてちょっと感心した。でもそれは過去に戻るまで。最近タイムマシンネタで面白かった映画(元は舞台らしいけど)の『サマータイムマシン・ブルース』みたいに、タイムマシンという道具立てを使い倒す話ではなくて、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1作目)のように単純に過去に遡って、帰ってくるだけ。
バブル崩壊を救うために過去に行くという設定も、その裏の陰謀もまあストーリーを展開させるためだけで、予想通り当時の流行が今見るとやっぱりおかしいというのをついたコメディ。
とはいえこの17年前を笑い飛ばすのは面白い。17年前を笑うだけでなく、現代の広末涼子が過去で浮いているのも面白い。ただこの笑い、17年前を知っている人のほうが面白いんじゃないか。17年前は5歳で、バブルを全く知らない主人公(広末涼子)が、そのギャップに驚くというわけで、広末と同じ立場で観客は笑うのかもしれないが、このギャップが本当に笑えるのは17年前を知っている今40歳前後か、それ以降の人じゃないかと思う。一番映画を観にくる世代=バブルを知らない世代=ターゲットの客層と、笑いの質がうまくマッチしていないような気がする。派手に宣伝している割には、人の入りはいまいちだったような気がしたのはそのせいかも。
ディテールとしては、ラモス瑠偉や飯島直子が本人役で出てくるとかいう遊びはありがちだが、タイムマシンが日立製だったり、潰れた銀行として長銀の名前が出てきたり、というのはあんまりない。と思ったら脚本は君塚良一なのね。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』的な話なので、当然結末で現代に帰ってきたとき、どうなるのかが気になるところ。でもこれは特に落ちなし。特に難しいことを考えずに、笑って終われる。
しかしSF好きとしては、ちょっとしんみりもしたりして。というのは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の過去が変わると、未来が徐々に変わっていくという設定ではないところ。写真の影が薄くなったりとか、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の未来の変わり方はあまり好きではないのたが、ハッピーかどうかという観点では文句なしにハッピーになれる。
しかし『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』の未来は別の時間軸が存在する未来になっていた。っていうことは、『夏への扉』でピートが不幸になっている時間軸もあるのかもしれないという切なさがあるように、広末涼子の帰ってこないまま日本経済の崩壊を迎える阿部寛の時間軸もあるかもしれないんだよね。
permalink | 
『幸せのちから』をMOVIXさいたまで観る。
「全財産21ドルから立ち上がった父子の、実話に基づいた感動作。」と惹句にあるが、特に感動しなかった。アカデミー賞ノミネートだし、評判もよさそうだったけど、心に沁みるとか胸を打たれるとかそういう感動はしなかった。ただ、確かにすごいとは思った。最悪の事態でも諦めずに、株式仲買人になる。
クリス・ガードナー(ウィル・スミス)は医療器具のセールスマンをしているが、思うように売れず厳しい生活を送っている。そんなある日、いい車に乗り幸福そうな顔をした男に話しかけて、株式仲買人の話を聞く。学歴を問わず採用の門戸は開かれているのを知り申し込むが応募者は多数いて面接すら簡単に出来そうにない。持ち前のやる気で面接官にアピールし無事面接に漕ぎ着けるが、見習い期間の半年は給料はなく、その見習い期間後にも採用されるのは20人に一人という厳しい現実を知る。
その一方で、妻には愛想をつかされて出て行かれてしまう。面接は成功裏に終わるが、息子を手放したくない彼は無給で半年間の見習いなど無理だと一度は諦めかける。しかし医療器具を売って見習いをすることを決める。そして運良く医療器具も売り切り、見習い生活へと入る。だがその運も一時的なもので、家賃の滞納のつけで家から追い出されモーテル暮らし。滞納していた税金の請求で手持ちの金は21ドルとなり、モーテルでも滞納するうちに閉め出しをくう。
泊まるあてもなく、駅のトイレで息子と一晩過ごす。翌日からは教会の慈善宿泊施設に毎日行列に並んで泊まる。全財産を持って仕事に出かけ、帰りは人より早く勤務を切り上げ宿泊の順番待ちをする。短い勤務時間で、人より多く客を獲得し、夜も自己研鑽を欠かせない。20人のうちの一人に残るには並大抵の苦労では生き残れないのだ。
すごいと思ったのは、住むところもなくなった時点で、息子を母親の元に預けるなりなんなりするのかと思ったが、最後まで息子を手放さなかったあたりだろうか。でも、結局守るべき息子という存在が彼を頑張らせたのだという気もする。そうは思うが、だからといって誰にでもできることじゃない。
前半、売れないセールスマンをしている頃は、笑えるエピソードもあるが、金も住む場所もなくなるあたりからはもう重苦しく、観ているのもちょっと辛くなるような話である。いい話とか、泣かせる話とかいうよりも、なんかもうただ悲惨でそれでも頑張るすごい話というのが強かった。最後に採用が決まる場面では、ウィル・スミスが涙を浮かべていても、成功や感動を盛り上げるのではなくて映画は淡々と静かに描く。そういう描き方はすごくいいし、まさにここは泣くところなのかもしれないが、苦労が報われたというより、これ採用されて当然だろうという感じですんなり受け入れてしまった。
駄目な男の側面も描かれているのだけれど、すごい部分の方が印象が強いのかもしれない。やっぱり、こういう話では駄目なやつでないと、感動にならないのかもしれない。
permalink | 
|
|
|
|
 |